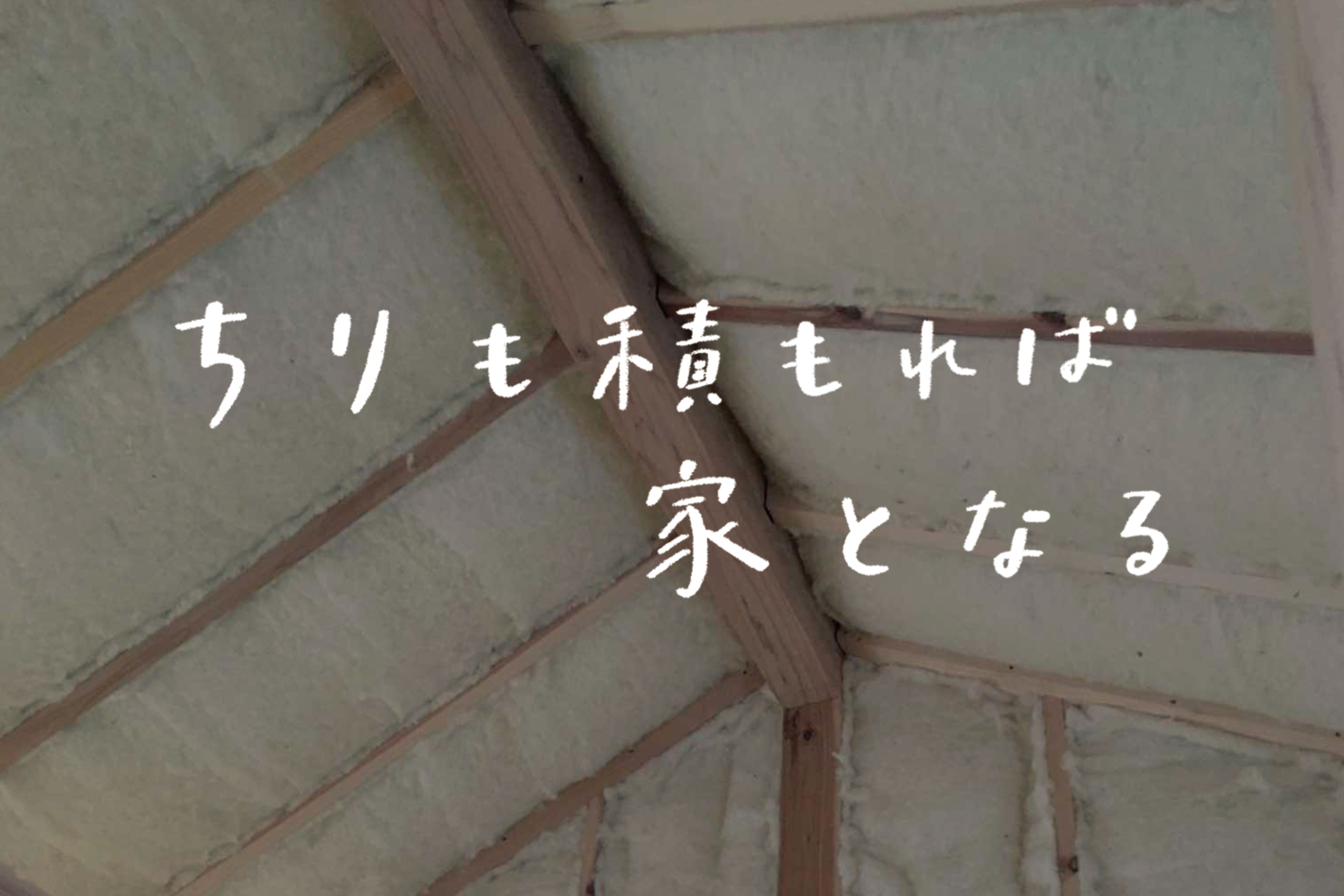こんにちは。広報の井上です。
先日、相模原にある刻み小屋「相模原ベース」へ行ってきました。

この日行われていたのは、新社屋に使用する構造材の「墨付け作業」でした。
「墨付け」とは、柱や梁をどう組み合わせるかを考えながら、向きや位置、どこを切り、どこに穴を開けるかといった加工の指示を、墨で木材に記していく作業のことです。
柱や梁、桁などが正確に組み上がるよう、下準備をしていく大切な工程。
木の性質を一つひとつ見極めながら進めるこの作業は、手刻みに欠かせない重要なプロセスでもあります。

中村大工は、設計士が描いた図面を受け取ると、それを基にまず「手板」を起こすそうです。
手板とは、柱の位置、梁の長さ、継手・仕口の形状を細かく描き込んだ大工専用の作業図(図板とも呼ばれます)で、これをもとに墨付けを行っていきます。

墨付けの後は刻み作業へ
墨付けが終わると、いよいよ刻み作業に移ります。
中村大工曰く、「墨付けがしっかりできていれば、それを見ながら刻むだけだから、刻み自体は実はそんなに難しくない」とのこと。
わずかな誤差が建物の強度や耐久性に直結するため、やはり墨付けこそが手刻みの肝なのだと感じました。

墨付けに欠かせない道具が、墨つぼと墨さし。
墨つぼに入れた墨を、へら状の道具「墨さし」で木材に線や文字として記していきます。
中村大工は、木製で龍の彫刻が施された愛用の墨つぼと、竹を削り自作した墨さしを使っていました。
こうした道具からも職人のこだわりが伝わってきます。

刻み小屋に積まれた無垢材
小屋の中には、ざっと見ただけでも、100本?150本?ほどの構造材が積み上げられていました。
中には長さ6mを超える材も……!
「井上さん、ちょっと持ってみてよ」と言われて挑戦してみるものの、もちろん持ち上がりません。
これを一人で運んだり動かしながら作業しているかと思うと、大工仕事がいかに体力勝負の重労働か、改めて実感します(土台敷きの時も思いましたが…)。

手刻みが減る時代に、それでも続ける理由
前回のブログでも書きましたが、今の木造住宅の多くは、「プレカット」と呼ばれるコンピュータ制御の機械によって構造材が加工されます。
スピード、精度、コストの面で優れているため、現在の住宅業界ではプレカット材が主流となり、手刻みができる職人は年々減少しています。
力を発揮できる現場も限られ、技術の継承も難しくなっているのが現状です。

そんな中、中村大工は「手刻みの現場は、いつも以上に気合いが入る」と話してくれました。
難しいけれど面白い。そこには、単なる加工を超えた、職人としての喜びがあるように感じました。


無垢材は生きた素材
これも前回も書きましたが、無垢材は自然素材です。
反ったり、ねじれたり、曲がったり、歪んだり……一本一本がまるで人間のように違う表情を持っています。
木材の反りやねじれといったクセやばらつきを抑え、寸法や強度を安定させるために、高温乾燥や、合板・集成材といった加工技術が生まれました(もちろん、施工性や大量生産の効率化など他の目的もあります)。
一方、天然住宅では「木材」をよく知っている大工に木を活かしてもらいます。
目で見て、頭で想像し、経験で見極めながら適材適所に配置し、手で刻んでいく。
その結果、反りや捻れも最小限に抑えることができます。

上の写真の一番手前に写っているのは、「金輪継ぎ(かなわつぎ)」という継手。梁と梁を強固につなぐ高度な加工で、プレカットではできないそうです。
熟練の技術が必要とされるため、使いこなせる大工も限られています。

また、手刻みならではの「番付(木材の位置情報)」も印象的でした。一本ずつ手書きで書き込まれることで、人の手による温かみが生まれます。
この日は黙々と作業に集中していた中村大工ですが、普段は耳元で音楽を流しながら(けっこうな声量で!)歌いながら刻んでいるのだとか。
真剣に木と向き合うなかにも、どこか楽しげな雰囲気が流れているのですね。
想像すると、なんだか微笑ましくなります。

そんな中村大工の姿を、この日はたっぷり撮影させてもらいました。
匠の技を、少しでも感じていただけたら嬉しいです。
完成した動画は >>インスタグラムからご覧ください!