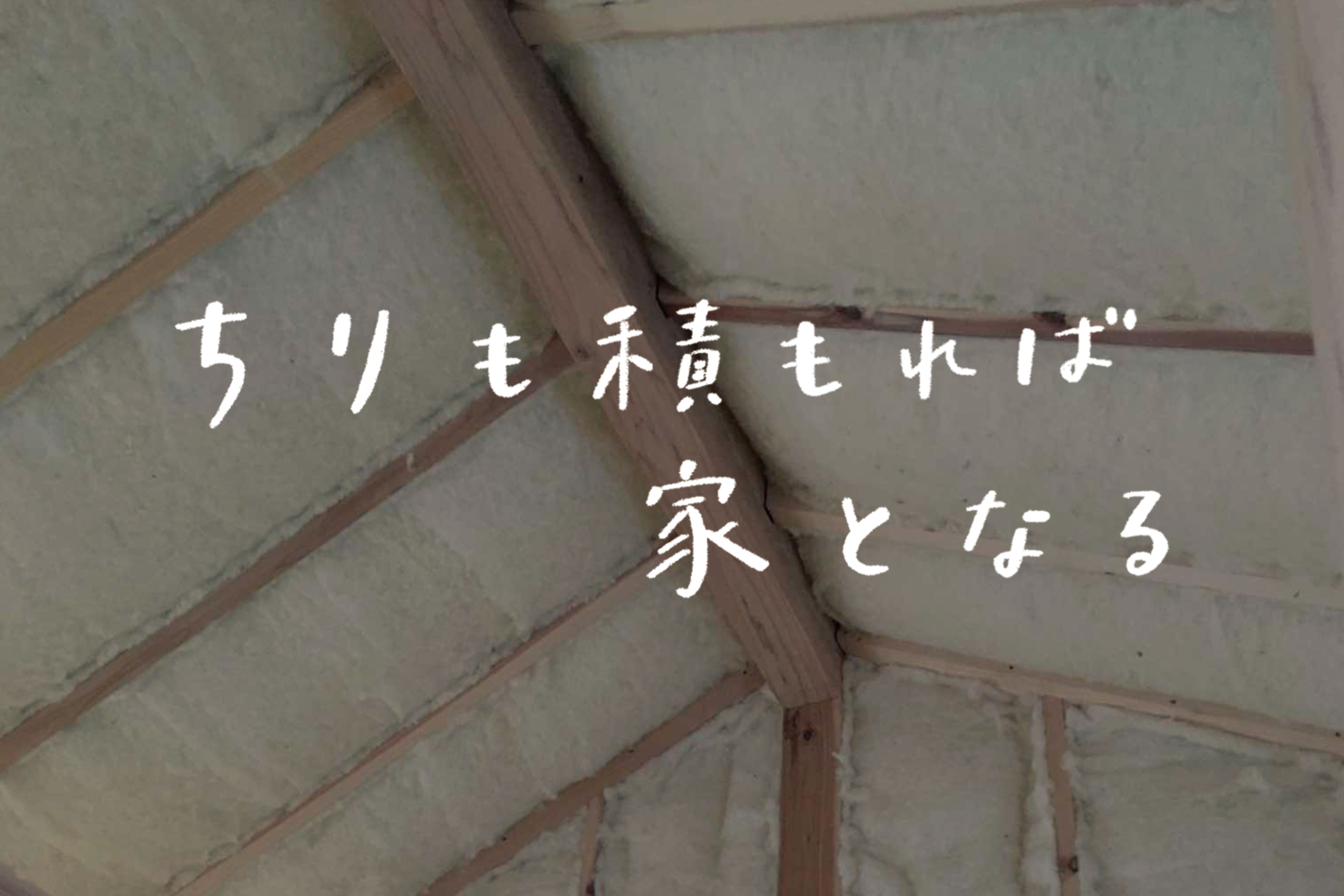こんにちは、広報の井上です。
7月上旬、新社屋兼モデルハウスが、ついに上棟を迎えました!
当日は、棟梁の中村大工をはじめ、5人の大工さんたちが集結。
息の合ったチームプレーで、流れるように正確に、作業を進めてくださいました。

15時頃には無事に棟が上がり、骨組みが完成。
これまで何度も見てきた光景ですが、やっぱり自分たちで使用する建物となると、喜びもひと塩ですね!(建主様の気持ちにまた一歩近づけた気がします)。
ここからは当日の様子をご紹介します。
私が現場に到着したのは10時ごろ。
すでに2階の柱まで据えられていました。



職人さんたちの朝は早いんです。
中には「6時前に家を出たよ」という方も。
私たちの家づくりのために、こんなにも早朝から……本当にありがたいです。

この日も、梅雨とは思えない晴天でした。
気温はぐんぐん上がり、立っているだけでも汗が吹き出してくるほど。
そんな中でも、大工さんたちは重装備。ヘルメットを被り、腰に重い道具を下げ、大きな木材を抱えて、足場の悪い高所を軽やかに動き回ります。
素人なら煽られてしまうような風にもびくともせず。
木材を組み上げ、木槌を振るう姿には、いつものことながら見惚れてしまいます。



クレーンを操る操縦士の方も、現場をじっと見つめながら、タイミングを見計らって材を吊り上げていきます。
ハンドルを握っていない時も、次の動きを見越して集中しているのが伝わってきて、その眼差しのカッコいいこと!

中村大工の現場には、いつも信頼する仲間の大工さんたちが応援に駆けつけてくれます。
旧知の間柄という方も多く、まさに“阿吽の呼吸”。
見事な連携でテンポよく作業が進み、時折聞こえてくる笑い声からは、現場の和やかな空気が伝わってきました。
この日はスタッフも次々と現場を訪れ、いつもよりギャラリーの多い一日になりました。

以前、中村大工の「刻み」の様子を見学に来てくれた中学生のTくんが、学校の先生と一緒に来てくれました。
彼の将来の夢は、「国産の木で、家も家具もつくれる職人になること」。
上棟の現場を見るのは初めてだったそうで、「ずっと見ていられる」と目を輝かせていました。

私自身、一日現場を見守る中であらためて感じたのは、「一棟の家づくりにはこんなにもたくさんの木を使うんだ!!」ということです。
これ、毎回毎回思うことですが、現場に立つと全身で感じ、圧倒されます。
ここに使われているのは、すべて国産の無垢材です。
宮城の山で50年以上かけて育った木を、木こりさんが丁寧に伐り出し、製材・乾燥の工程を経て、はるばる東京まで運んできました。
防腐剤などの化学薬品は使わず、低温燻煙乾燥という方法で、時間をかけてじっくりと乾かされた木材たち。
それらの木を、中村大工が一本一本見極めながら、すべて手刻みで準備してくださいました。
中村大工曰く、「この建物は、材料が語ってくれる」のだそうです。




これだけの木が集まっていると、まるで森の一部が街にやってきたような気持ちになります。
“天然住宅で家を建てるという営みは、森の中で飽和状態になっている木を街に移植し、新たな場所でもう一度森をつくる”
そんな営みとも言えるかもしれません。
そして私たちの役割は、この“森のような家”を100年以上もつように建て、住み継いでいってもらうこと。そんなふうに感じました。

△「込み栓」と呼ばれる広葉樹の堅木で接合部をつなぎます。金物を使うのは最小限で。

△天然住宅の家では、「落とし込み板」と呼ばれる、厚みのある無垢杉材を構造材として使用しています。1階の天井を兼ねたこの板が貼られると、まるで木陰にいるような心地よさに。日差しが照りつける中、木の下の涼しさにほっとします。

△落とし込み板を設置しているところ。構造部分にも合板は一枚も使用しません。

代表の田中も、「ここまで来られたのは、多くの人の力があってこそ」と感無量の様子。
実はこの日は、田中の40歳の誕生日でした。
「無事に、人生の“棟”が上がりました」と嬉しそうに話していました。
建主様の気持ちを体感できた、忘れられない一日になったのではないでしょうか。

建物の輪郭ができ、いよいよ本当に建つんだ!という気持ちに。
しかし天然住宅の家は、ここからがとっても長いんです。
いつも周りの住宅に追い越されます(笑)
大工さんによる手づくりの家ですから、仕方ありませんね。
すべて必要な工程なのです。
完成は年末頃の予定です。また進捗をご報告しますね。